「動機善なりや、私心なかりしか」——この短い言葉に、稲盛和夫の人生哲学は凝縮されています。
京セラ・KDDIの創業者であり、日本航空の奇跡的な再建を成し遂げた経営者として知られる稲盛氏ですが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。
成績不良や就職失敗、経営危機、大企業との競争、そして異業種での挑戦と再建…。
幾度も訪れた逆境を乗り越え、成功を手にした背景には、確固たる信念と「人を中心に据えた経営」がありました。
本記事では、稲盛和夫が歩んだ失敗からの逆転ストーリーと、その中で培われた人生哲学を、創業からJAL再建までの流れとともに紐解いていきます。
第1章|若き日の挫折と就職失敗
稲盛和夫は1932年、鹿児島市で7人兄弟の二男として生まれました。
幼少期は戦争の時代で、物資不足や混乱の中で育ちます。
小学生の頃には肺結核や肋膜炎を患い、死の危険さえあるほどの重病で長期入院を余儀なくされました。
この経験は、のちに「健康で働けることのありがたみ」を深く心に刻むきっかけとなります。
高校時代は成績不振で大学進学すら危うく、教師からも厳しい評価を受けていました。
周囲の同級生が進学や就職を順調に決めていく中、自分には特別な才能やコネもなく、将来に希望を持てない時期が続きます。
ようやく鹿児島大学工学部に進学したものの、卒業後の就職活動では企業から相次いで不採用通知が届きます。
理由は「大学の知名度の低さ」「体が弱そう」という先入観もあったとされます。
最終的に内定を得たのは、京都にある小さな絶縁材料メーカー「松風工業」でしたが、この会社は入社間もなく経営難に陥ります。
倒産の危機を目の当たりにし、「自分の未来は自分の力でしか切り開けない」という強い覚悟を抱くようになりました。
筆者のひとこと
病気や成績不良、就職失敗…普通なら心が折れてもおかしくない挫折の連続です。
それでも諦めず次の一歩を探し続けたからこそ、後の大逆転につながったのだと思います。
第2章|京セラ創業とゼロからの経営
27歳のとき、稲盛は仲間7人と共に「京都セラミック株式会社」(のちの京セラ)を設立します。
資本金はわずか300万円、創業メンバーも営業経験のない技術者ばかりでした。
製品は高品質なファインセラミック部品でしたが、当時はその市場自体がほとんど存在せず、販路をどう切り開くかが最大の課題でした。
稲盛は営業マンとして全国を飛び回り、企業の技術部門に直接アポイントを取り、試作品を持ち込んでは品質を説明しました。
時には断られ続ける日々が続き、旅費を節約するために夜行列車や安宿を利用しました。
初めての大口契約は、テレビメーカー向けの部品供給。
納期を守るために社員総出で徹夜作業を行い、この誠実さが信頼を呼び、次第に取引先が増えていきます。
稲盛は経営方針として「アメーバ経営」を導入。
小集団単位で収支を管理し、社員一人ひとりが経営者意識を持つ仕組みを作りました。
また、「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念を掲げ、利益だけでなく社員の成長や生活の安定を最優先しました。
結果として、創業10年足らずで京セラは東証二部に上場、さらに世界市場にも進出していきます。
筆者のひとこと
創業期にこれだけの行動量と理念の徹底を同時にやるのは並大抵ではありません。
「人を大切にする経営」が利益にも直結することを、稲盛さんは体現していました。
第3章|KDDI誕生と通信事業への挑戦
1990年代後半、日本の通信業界は規制緩和により新規参入が可能になり、激しい競争時代に突入していました。
当時、稲盛が率いていた第二電電(DDI)は、固定電話の長距離通信を手がける新興企業として成長していましたが、既存のNTTが圧倒的なシェアを握っており、価格競争や設備投資の面で常に不利な立場でした。
稲盛は「通信は21世紀の基盤産業になる」と確信し、携帯電話事業やインターネット通信へ積極的に参入します。
さらに、競争力を高めるためにKDD(国際通信)とIDO(携帯電話事業者)との合併を主導。
この大型再編により、2000年にKDDIが誕生しました。
KDDIはスタート時から赤字を抱え、既存大手に比べ知名度も低かったため、加入者獲得は困難を極めます。
しかし稲盛は、「料金は正直に、サービスは誠実に」という方針で、業界最安値に近い料金体系と、地方まで行き届く通信網整備を進めました。
やがて、シンプルな料金プランや地方での安定した通信環境が口コミで広がり、シェアは着実に拡大。
KDDIはNTTドコモに次ぐ国内2位の通信事業者へと成長しました。
筆者のひとこと
巨大企業との真っ向勝負に挑むには、普通なら尻込みします。
でも稲盛さんは「勝算は理念と人材力にある」と信じて突き進んだ。これは現代のスタートアップにも通じる考え方だと思います。
第4章|JAL再建の奇跡
2010年、日本航空(JAL)は経営破綻し、戦後最大規模の企業再生案件となりました。
当時78歳だった稲盛は、既に現役を引退していたにもかかわらず、政府や経済界からの要請を受け、無報酬で会長職に就任します。本人は「航空業界は全くの素人」と語っていましたが、日本経済にとっての航空会社の重要性を理解し、覚悟を決めました。
稲盛が最初に行ったのは、徹底的な現場視察です。
パイロット、客室乗務員、整備士、地上スタッフ…あらゆる職種の声を聞き、経営陣と現場の間にある深い溝を把握しました。
再建の柱は、「心を高める経営」と「アメーバ経営」。
部門ごとの収支管理を徹底し、社員一人ひとりがコスト意識を持てる仕組みにしました。
同時に、「お客様第一主義」を再教育し、社員の士気を高めました。
結果、わずか2年で経常利益2,000億円を達成し、2012年には再上場を果たします。
このスピード再建は、世界的にも驚異的な成功事例とされました。
筆者のひとこと
経営再建と聞くと数字の立て直しばかりを思い浮かべますが、稲盛さんはまず「人の心」にアプローチしました。
この順番が、最短で結果を出せた最大の理由だと思います。
第5章|稲盛哲学が現代に残したもの
稲盛和夫の人生哲学は、一言でいえば「動機善なりや、私心なかりしか」に集約されます。
これは「その行動の動機は正しいか、そこに私利私欲はないか」という自問自答を常に行うべき、という教えです。
稲盛はこれを経営判断だけでなく、人間関係や日常生活のあらゆる場面で適用していました。
この哲学の背景には、創業期やJAL再建で経験した「理念なき利益追求は必ず行き詰まる」という確信があります。
短期的な利益を追うあまり社員を疲弊させたり、顧客との信頼を損なう企業は、いずれ衰退することを多くの現場で見てきたのです。
稲盛はまた、「利他の心」を経営の中核に据えました。
これは単なる道徳的スローガンではなく、利他こそが最も合理的な戦略だという実践的な考え方です。
例えば、社員が働きやすい環境を整えれば生産性は上がり、顧客満足度も自然に向上します。
結果として企業は安定して利益を上げられる——この循環を何度も証明しました。
さらに稲盛は、自身が編み出した「アメーバ経営」を通じて、経営哲学を現場の全員が実践できる仕組みにしました。
これは経営理念を単なる掛け声に終わらせず、数字と日々の行動に落とし込むための道具として今も多くの企業に導入されています。
現代においても、この哲学はスタートアップから大企業、そして個人事業主にまで応用可能です。
目先の利益や競争に追われがちな時代だからこそ、「動機善なりや」という問いは、事業の軌道修正や信頼構築の羅針盤になります。
筆者のひとこと
私自身も、迷ったときはこの言葉をビジネスのフィルターとして使おうと思います。短期的な儲け話に飛びつくより、信頼と理念を守ることが、結局は一番の近道だと感じます。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
みなさんのビジネスの理念は何ですか?是非教えてくださいね!

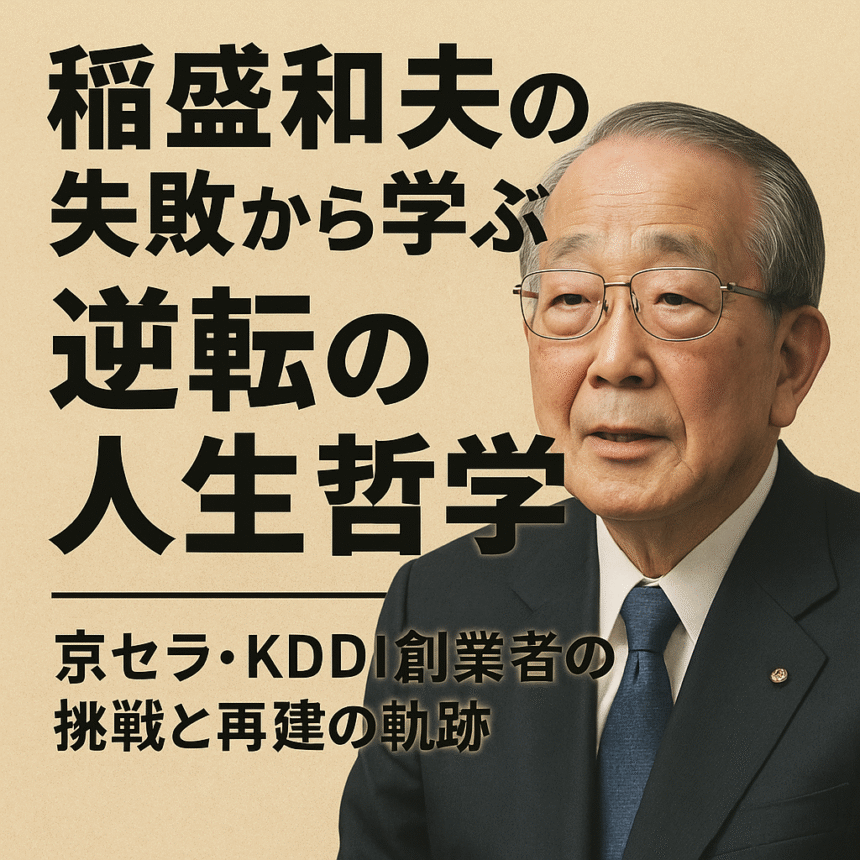
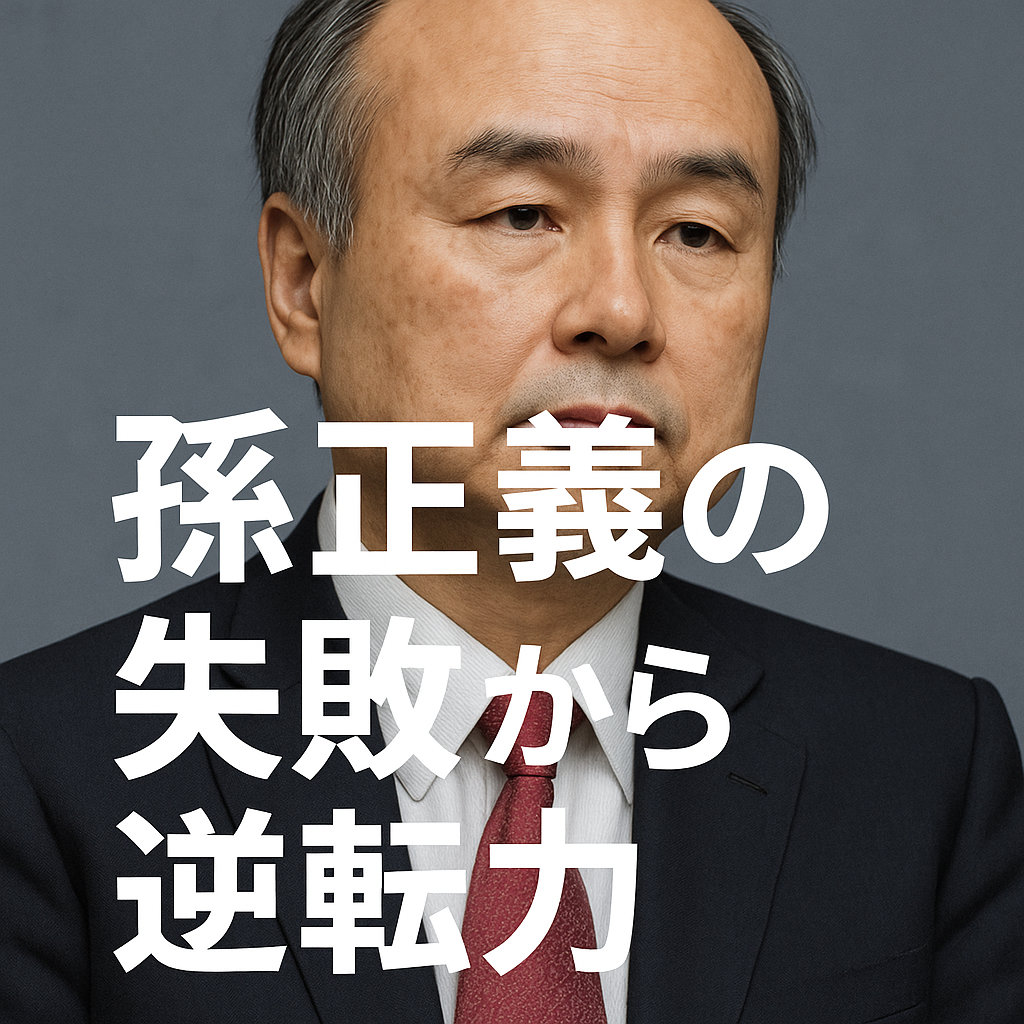

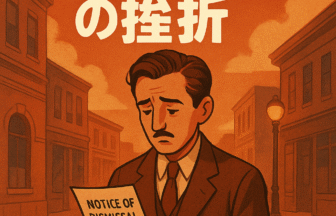



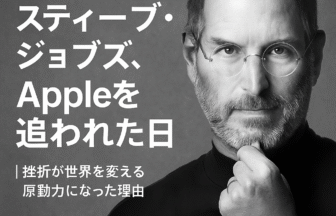
この記事へのコメントはありません。