今日は誰もが知る日本の社長、楽天の三木谷社長をご紹介します!
どんな成功者でも、最初はやはり一筋縄ではいっていないということをぜひ皆さんにシェアさせてください!
1章|外資系エリートの脱サラと最初のつまずき
三木谷浩史氏は、一橋大学を卒業後、米国留学を経てゴールドマン・サックス証券に入社。
金融マンとして順調なキャリアを積み、年収や社会的地位も安定していました。
しかし1990年代後半、米国でのインターネットビジネスの急成長に刺激を受け、「日本にも必ずECの波が来る」と確信。
安定を捨てて起業の道を選びます。
1997年に資本金2,000万円で「MCI株式会社(現・楽天グループ)」を設立し、楽天市場をスタート。
しかし、当時の日本ではネット通販はほぼ無名で、PC普及率も低い時代。
オープン初日の出店店舗はわずか13店。
1日の来訪者数は数百人レベル。
広告を出しても反応はほとんどなく、三木谷氏の周囲からも「無謀だ」と批判されました。
さらに、銀行融資の申請も「前例がない」と断られ、資金繰りは早くも厳しい状況に追い込まれます。
筆者のひとこと
安定収入を手放す勇気と、ゼロからの挑戦の現実。このギャップの大きさは、想像以上に精神的な負荷があったはずです。私も収入源を手放して新事業を始めたとき、周囲の反対と現実の壁に直面しました。
2章|「手作り」営業と赤字続きの現実
当時、楽天市場の営業活動は完全に人力。
インターネットでの商売経験を持つ企業はほとんどなく、出店交渉は1件ずつ飛び込み訪問するスタイルでした。
さらに、写真撮影や商品ページ作成も出店者側ではなく楽天側が担当。
送られてきた商品写真は紙焼きだったため、スキャナーで読み込み、手作業でアップロード。
契約書も郵送またはFAXでやり取りし、ウェブ上の管理システムはほぼ存在しない状態でした。
それだけ苦労しても、最初の1年は赤字が続きます。
売上は少しずつ増えても、広告費や人件費、インフラコストが重くのしかかりました。
資金は減る一方で、三木谷氏は「社員の給与遅配も覚悟しなければ」というところまで追い詰められます。
筆者のひとこと
IT企業の黎明期は、今のような自動化や便利なツールがなく、ほぼ全てが人海戦術。利益が出る前に資金が尽きる恐怖は、どの時代の起業家も共通の課題だと感じます。
3章|逆転のきっかけは“楽天スーパーポイント”
2002年、三木谷氏は売上とリピート率の伸び悩みを打破するため、楽天スーパーポイントを導入しました。
当時のEC業界ではポイント制度は珍しく、導入当初は「原資負担が増えて利益が減る」と出店者から反対の声もあがりました。
三木谷氏はその不安を払拭するため、数値シミュレーションを提示。
「ポイントを還元しても、顧客が戻ってくる確率が上がれば最終的に売上は増える」という理論を説明し、さらに導入後は効果測定のデータを共有しました。
加えて、出店者の売上アップを目的とした“ECの学校”型研修を定期開催。
- 商品タイトルや説明文の改善
- 写真撮影の工夫(ライティングや背景の使い方)
- 顧客対応のマナーや迅速な発送方法
これらのノウハウを共有することで、ネット初心者だった店舗でも成果を出せるようになり、店舗数と顧客数が同時に増加していきます。
筆者のひとこと
ポイント制度は“ただの値引き”になりがちですが、楽天は教育プログラムと組み合わせて顧客体験を底上げしたのが勝因でした。
4章|世界進出と再びの壁
国内市場での成功を背景に、2000年代後半から楽天は世界市場へ進出します。
特にフランスのPriceMinister買収は、当時「日本企業による海外EC買収」として話題になりました。
アメリカではBuy.com、英国ではPlay.comなどを買収し、一気にグローバルネットワークを築こうとしました。
しかし、実際にはいくつもの壁が立ちはだかります。
- 文化の違い:日本ではポイントや顧客サポート重視が効果的でも、海外では価格重視や即日配送が当たり前で、楽天モデルがそのまま通用しなかった。
- システム統合の難航:各国のECサイトは決済方法や物流システムが異なり、共通基盤に統合するのに莫大な時間と費用がかかった。
- 現地経営陣との摩擦:買収後の方針転換に対する反発や、経営権をめぐる意見対立が発生。
結果的に、米国市場など一部は撤退。数百億円規模の損失を計上する苦しい決断もありました。
筆者のひとこと
グローバル展開は華やかに見えますが、現地文化や既存システムの壁は予想以上に高いもの。日本式の成功モデルをそのまま輸出する危うさを感じます。
5章|楽天モバイルの挑戦と巨額投資
2019年、楽天は携帯電話事業に本格参入しました。狙いは「楽天経済圏」をリアルの通信インフラまで拡大すること。
これにより、ECや金融サービスの顧客をモバイルでも囲い込み、ポイントとサービス利用を連動させる戦略でした。
しかし、この決断は非常に高リスク。
携帯キャリアになるためには、全国規模の基地局整備が不可欠で、その投資額は数千億円規模にのぼります。
初期は基地局数が足りず、都市部を離れるとすぐ圏外になることも多く、SNSや口コミで批判が殺到。
さらに通信品質改善のための追加投資が必要になり、赤字は累計で数千億円に達しました。
それでも三木谷氏は、クラウドベースの通信ネットワーク「仮想化ネットワーク(Open RAN)」を採用し、設備コスト削減を図ります。
海外展開も視野に入れ、この技術を輸出ビジネスに転用する構想も持っています。
筆者のひとこと
普通の企業なら赤字が膨らめば撤退を検討しますが、三木谷氏は「通信事業は時間がかかる」ことを理解し、長期戦を前提に動いているのが印象的です。
6章|“失敗”を糧にする楽天流経営
三木谷氏は経営哲学として「失敗を恐れず、次に活かす」を掲げています。
彼の失敗は単なる過去のエピソードではなく、次の戦略の材料です。
- 楽天市場の立ち上げ期 → 「顧客教育と出店者支援」の重要性を学び、ECの基礎体制を確立
- 海外事業の撤退 → 「現地文化適応とローカル戦略」の必要性を痛感
- 楽天モバイルの赤字 → 「短期損失より長期シェア」を優先する意思決定
楽天グループは今や、EC、金融、旅行、スポーツ、通信など多岐にわたる分野に展開。
どの事業にも“過去の失敗から得たノウハウ”が息づいています。
三木谷氏は、挑戦を続ける理由についてこう語っています。
「失敗を恐れて何もしないことが、最大の失敗だ」
筆者のひとこと
私も新規事業で失敗するたびに、この言葉を思い出します。短期的な失敗は長期的な成長のための材料になると考えれば、挑戦するハードルは下がります。
いかがでしたでしょうか。
みなさんは失敗を恐れていますか?それとも恐れていませんか?
この質問だけでも、ハッと気づかされることはあるのではないでしょうか。
ということで、最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
ぜひみなさんの失敗エピソードを取材させてくださいね!

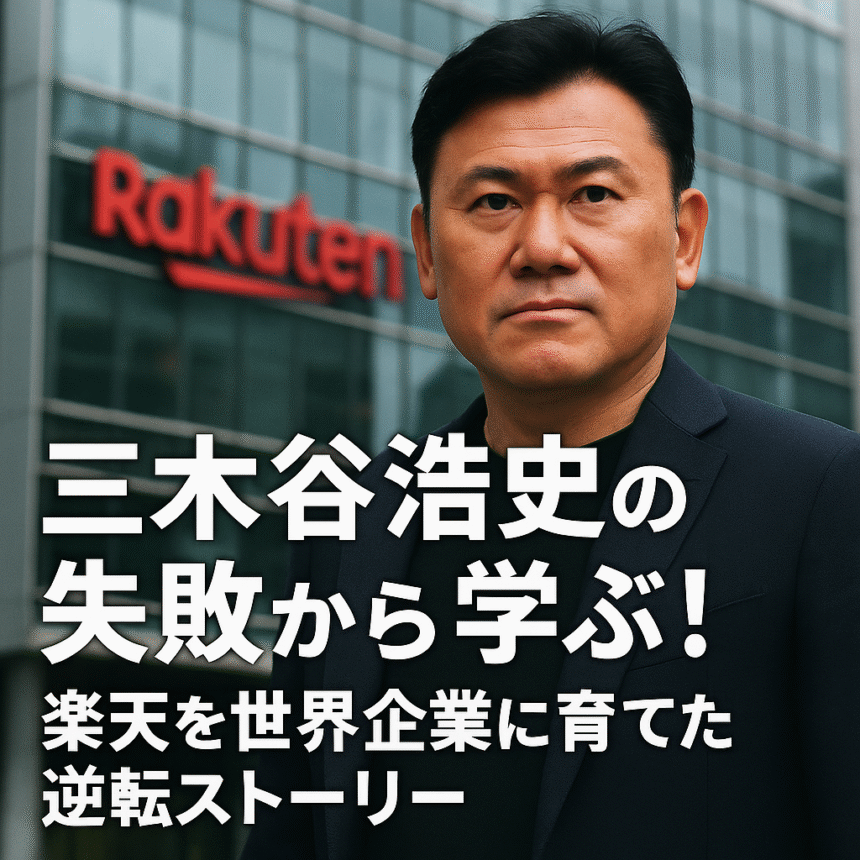


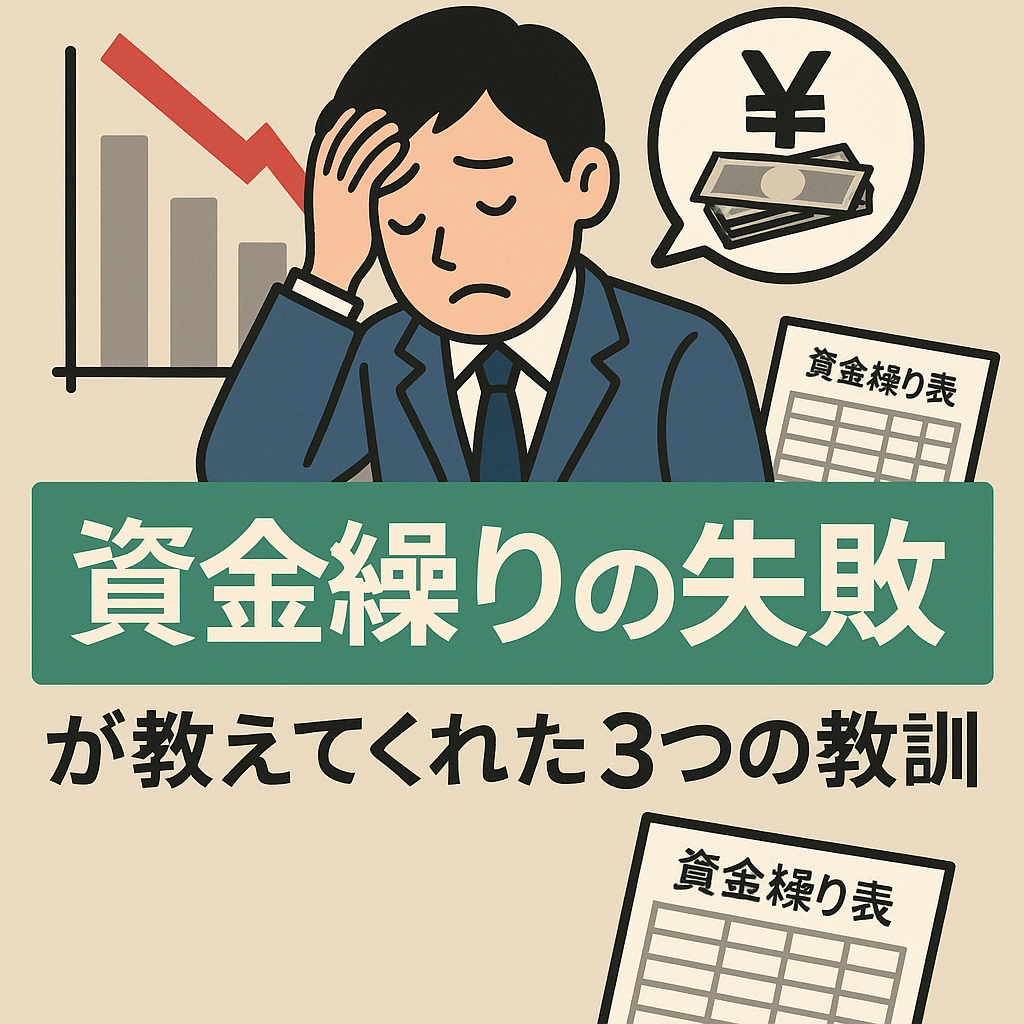
この記事へのコメントはありません。